「映像資料の保存」と聞くと、多くの方が“劣化を防ぐ”という保管中心のイメージを持つかもしれません。
しかし、視聴覚資料の役割はそれだけにとどまりません。
現代では視聴覚資料は、単なる「過去の記録」ではなく、未来に活かすことのできる「文化的・経済的資産」として再評価されています。
本記事では、「映像や音声は資産である」という視点から、視聴覚資料の価値、活用方法、そしてデジタル化を通じた未来への継承方法について、専門的な観点から整理して解説していきます。
資産としての視聴覚資料とは何か
一般的に「資産」と聞くと、多くの人が不動産や株式、現金、設備などの“有形資産”を思い浮かべます。
しかし、近年は、「文化資産」「知的資産」「情報資産」といった無形資産の重要性が世界的に高まっています。
企業のブランド価値、地域の文化資源、個人の記録なども、経済的・社会的な価値を持ち得る時代が到来しているのです。
家庭のホームビデオ、企業のプロモーション映像、自治体の地域行事記録などは、単なる思い出や業務記録にとどまらず、後世にとって貴重な社会的・文化的証言となります。
とくに、日常の風景やその時代ならではの働き方・商店街・学校行事などは、後年になって初めて意味が顕在化する「潜在的資産」です。
 KO-ONくん
KO-ONくん昔のホームビデオなんて“家族だけの思い出”じゃないの? 資産ってほど重要なの?



確かに当時は“家庭の記録”として撮られていますが、将来にとっては“その時代の生活文化を知る証拠”になります。暮らし、服装、街並み、価値観などが細かく記録されているからです。
視聴覚資料は「過去を残す」だけでなく、「未来に新しい価値を生み出す」ための資産になりうるのです。
映像・音声はどうやって“価値を生む”のか?
視聴覚資料が資産としての価値を持つ理由は、その活用によって新たな意味や経済的価値を生み出せる点にあります。たとえば、以下のような活用事例があります。
- 昔の企業CMを使った周年記念動画の制作
- 昭和時代の街並みを映した映像を観光プロモーションに活用
- ホームビデオがテレビ番組やドキュメンタリーで引用されるケース
- 地域の記録映像が郷土教育・展覧会・地域史研究として再利用される例
- 工場作業の記録映像が技術継承・社内研修に活用
これらに共通するポイントは「保存されているだけでは価値が生まれない」ということ。
視聴覚資料の価値は、“使える形で整理され、必要なときに活用できる状態になっていること”によって初めて発揮されるのです。
そのために欠かせないのが、適切なデジタル化・アーカイブ化です。



“保存してあるだけじゃダメ”って、どうして?



活用されなければ価値を生むチャンスが永遠に来ないからです。アナログのまま眠っている映像は、検索も共有もできず“活用の入り口にも立てない”状態なんです。
海外の先進事例に学ぶ ― アーカイブから資産活用へ
海外では、視聴覚アーカイブを資産として戦略的に活用する動きが活発です。
たとえば、イギリスのBFI(英国映画協会)は、国内の映像文化を守るだけでなく、再利用可能なデジタルアーカイブを構築し、映像制作や教育現場に広く活用しています。単なる保存だけでなく、「文化資源を社会へ還元する」という明確な目的があるのが特徴です。
米国のスミソニアン協会は、映像・音声資料を展示だけでなく研究・教育カリキュラムに組み込み、地域史研究や社会文化の研究基盤の一部として運用しています。
これらの機関に共通しているのは、「アーカイブ=収蔵庫」ではなく、「アーカイブ=資源」であるという考え方です。日本においても、こうした視点が必要とされてきています。今後は、アーカイブを「社会的資産」として戦略的に扱う視点が不可欠です。
眠る資産を掘り起こすためのステップ
では、家庭や企業、自治体に眠る映像資産をどのように「使える資産」に変えていけば良いのでしょうか。
以下のステップが有効です。
再生可能なメディアか、内容は何か、破損していないか、保管状態はどうかを確認します。
メディアの種類(VHS・Hi8・8mmフィルムなど)や状態の把握は、後の作業工程を決める重要な第一歩です。
アナログメディアの多くは磁気減衰・カビ・物理的劣化により時間とともに再生困難になります。
劣化が進む前に高品質でデジタル変換することで、内容の保全と活用の基盤が整います。
「何年の映像か」「どこで撮影されたか」「登場人物は誰か」「イベント名は何か」などの情報を整理すると検索性が向上します。
アーカイブの質は、メタデータの有無で大きく変わります。
活用方法の視点から逆算することが重要です。
社内資料・コーポレートサイト・展示会・周年イベント・教育教材など、用途が明確になると資料価値が最大化します。
このように、単なる「保存」ではなく、「活用を前提とした整理と変換」が、視聴覚資料を資産化する鍵となります。
あなたの手元にある映像・音声も、未来の文化資産になる
「これは昔のビデオだから価値はない」と思い込んでいませんか?
実は、ありふれた日常の記録こそが、後の時代にとって貴重な文化資料となることがあります。
- 家族の食卓の風景
- 商店街や駅前の様子
- 学校行事、地域の祭り
- 社内の働き方や工場の様子
これらはすべて、今を生きる人々が見落としがちな「記録されにくい日常」であり、将来の社会にとっては
「見たことのない過去」、貴重な記録になるのです。
企業の視点では、創業期の映像や社員インタビュー、社内行事の記録、工場作業の映像などが、企業の歴史やブランドストーリーを伝えるコンテンツ資産として機能します。
自治体にとっても、地域の映像記録は観光・郷土教育・地域アイデンティティ形成に活用できます。



古い映像って、現代の人にとってどんな魅力があるの?



当時の空気感や人々の生活が“生のまま”存在する点です。写真には写らない音・動き・雰囲気が記録されているから、研究価値も文化価値も高いのです。
私たちができること ― 資料を活用につなげる修復とデジタル化
株式会社東京光音では、映画フィルム、ビデオテープ、音声テープといったアナログの視聴覚資料に対して、
「活用」を見据えた修復とデジタル化を行っています。単なるメディア変換ではなく、資料本来の価値を取り戻し、未来に活かせる資産として再生させることが私たちの使命です。
たとえば、
- カビが発生しているビデオテープや8mmフィルム
- テープが切れてしまったVHSやHi8
- 酢酸臭のするフィルム(ビネガーシンドローム)
- 劣化変形してしまった音声テープ
といった、一見「再生不可能」と思われるような資料でも、当社の独自の修復ノウハウや高度な再生・変換技術によって、映像や音声を蘇らせることが可能です。



カビが生えちゃったテープや酢酸臭のするフィルムって、もう終わりだと思ってた!



実は、専門技術による洗浄・修復を行えば復元できるケースが多いんです。むしろ自己流でいじる方が破損する危険があります。
これまであきらめられていた記録を蘇らせることで、その資料が「過去の遺物」から「未来に活かせる文化資産」へと姿を変えます。
家庭の思い出、企業の記録、地域の歴史――それらを未来へ手渡す第一歩として、修復とデジタル化による再価値化をご提案しています。
▶ 詳しくは 株式会社東京光音公式サイト をご覧ください。
まとめ:映像や音声を「資産」として未来へつなごう
視聴覚資料は、単なる記録を超えて、未来に新しい価値を生む可能性を秘めた資産です。
保存するだけでなく、整理し、価値を見出し、デジタル化し、活用する視点を持つことで、それは「文化的な資産」「情報的な資産」として新たな命を得ます。
今こそ、お手元の映像や音声を見直し、「未来の資産」として育てていきませんか?
著者:フィルム仕事人
フィルム・ビデオ・テープなどの映像・音声資産に関するお役立ち情報を随時発信しております!
東京光音は、映像・音声メディアのデジタルアーカイブを専門とする企業です。
映像・音声資産のデジタルアーカイブに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
長年の実績と確かな技術で、大切な記録を次世代へとつなぎます。
詳しくは公式サイト(https://www.koon.co.jp/)をご覧ください。
お問い合わせはこちらから
電話番号 03-5354-6510
問い合わせフォーム 【株式会社東京光音】お問い合わせフォーム
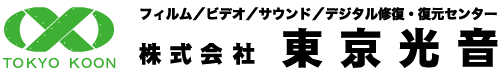


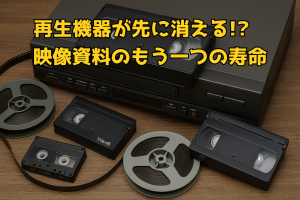

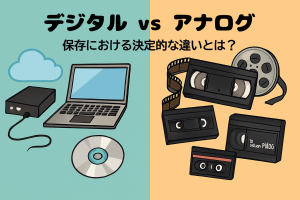


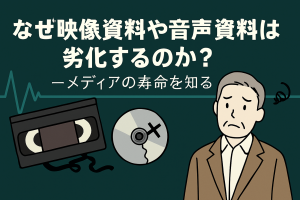
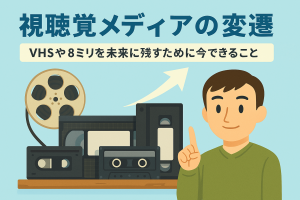
コメント